「武蔵野のくらし今昔―昭和の衣・食・住―」のミュージアムトーク@武蔵野ふるさと歴史館に行ってきました!①からの続き。
波田(はだ)学芸員のご説明のもと、まずは、「街並み(の移り変わり)」エリアから。
 三鷹駅北口の街並みは変わりましたが、銀杏は同じ場所にあり、立派に成長しているのがわかりますね、と波田学芸員。
三鷹駅北口の街並みは変わりましたが、銀杏は同じ場所にあり、立派に成長しているのがわかりますね、と波田学芸員。
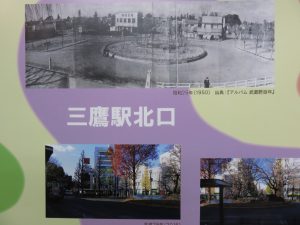 これが拡大図。三鷹駅北口の銀杏の成長ぶりに元気づけられます。
これが拡大図。三鷹駅北口の銀杏の成長ぶりに元気づけられます。
 各エリアごとに「むーくんポイント」があり、私たちに気づきのヒントをくれる仕掛け。小学3年生に戻った気分で考えます!
各エリアごとに「むーくんポイント」があり、私たちに気づきのヒントをくれる仕掛け。小学3年生に戻った気分で考えます!
 吉祥寺のバスターミナルの移り変わり。現在は柳沢行のバス停ですが、昭和40年(1965)の写真では東伏見行のバス停でした。
吉祥寺のバスターミナルの移り変わり。現在は柳沢行のバス停ですが、昭和40年(1965)の写真では東伏見行のバス停でした。
 パネルの下にはガラスケースが。昭和27年(1952)、市制5周年記念に作成された「武蔵野市全図」の実物。貴重です。(ちなみに今年は市制70周年🎊ですね。)
パネルの下にはガラスケースが。昭和27年(1952)、市制5周年記念に作成された「武蔵野市全図」の実物。貴重です。(ちなみに今年は市制70周年🎊ですね。)
続きまして、「衣(の移り変わり)」エリアへ。
 昭和20年(1945)頃、服=野良着(農作業用服)でした。各家庭で服を作り、直して、大切に着ていました。
昭和20年(1945)頃、服=野良着(農作業用服)でした。各家庭で服を作り、直して、大切に着ていました。
 ガラスケース内、裁縫道具一式。嫁入り道具の一つとして、一家に一セット必ずありました。服を「直して着る」ため、ボタンや型紙を取っておいて繰り返し使いました。
ガラスケース内、裁縫道具一式。嫁入り道具の一つとして、一家に一セット必ずありました。服を「直して着る」ため、ボタンや型紙を取っておいて繰り返し使いました。
 昭和10‐20年代の雑誌の付録の「型紙」。当時の流行の最先端だったのでしょうね、今見てもお洒落です♪特筆すべきは「付録」文化。近年復活の兆しを見せ、今も健在!継承されているものもあります。
昭和10‐20年代の雑誌の付録の「型紙」。当時の流行の最先端だったのでしょうね、今見てもお洒落です♪特筆すべきは「付録」文化。近年復活の兆しを見せ、今も健在!継承されているものもあります。
 当時の朝鮮半島の地図(超貴重!)を示しながら、この野良着の歴史を愛を持って語る波田学芸員。「仁川(インチョン。現在ソウルの空港がある港街ですね)」と書いてあり、当時現役で使われていた(であろう)布袋で作られた野良着。縫製修理された跡もあります。
当時の朝鮮半島の地図(超貴重!)を示しながら、この野良着の歴史を愛を持って語る波田学芸員。「仁川(インチョン。現在ソウルの空港がある港街ですね)」と書いてあり、当時現役で使われていた(であろう)布袋で作られた野良着。縫製修理された跡もあります。
 チェック柄のオシャレな野良着。
チェック柄のオシャレな野良着。
続いて、「食(の移り変わり)」エリアへ。
「武蔵野のくらし今昔―昭和の衣・食・住―」のミュージアムトーク@武蔵野ふるさと歴史館に行ってきました!③へ続く。

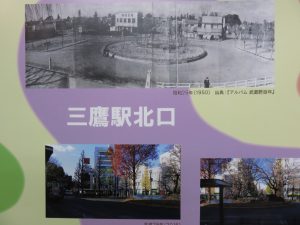








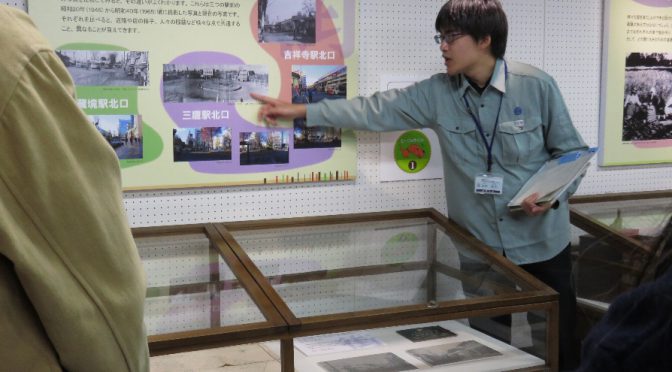

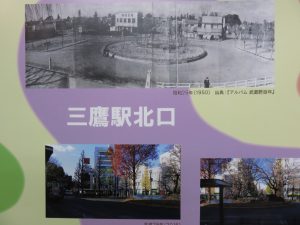








「「武蔵野のくらし今昔―昭和の衣・食・住―」のミュージアムトーク@武蔵野ふるさと歴史館に行ってきました!②」への3件のフィードバック